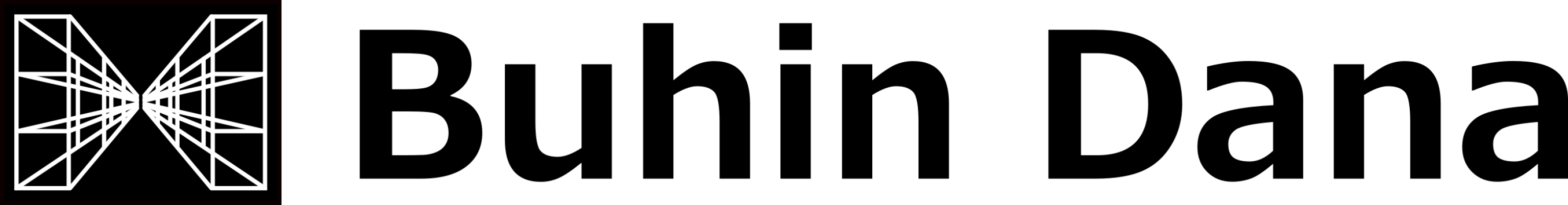プリント基板とは|BuhinDana
プリント基板とは、電子部品を搭載し、部品間を電気的に接続するための絶縁性の板のことです。現代のあらゆる電子機器に不可欠な部品であり、配線パターンによって複雑な回路を実現します。プリント基板があることで、電子機器の小型化、軽量化、高性能化、そして大量生産が可能になりました。




プリント基板の基礎知識
プリント基板は、私たちの身の回りにある様々な電子機器に使用されている重要な電子部品です。ここでは、プリント基板に関する基礎知識として、その役割や構造、主な材質について解説します。プリント基板の基本を押さえることで、電子機器がどのように成り立っているかの理解が深まります。
プリント基板の役割と機能
プリント基板の最も重要な役割は、電子部品間を電気的に接続することです。基板上に形成された銅箔などの配線パターンを通じて、電子部品が必要な信号や電力をやり取りします。また、プリント基板は電子部品を物理的に固定し、振動や衝撃から保護する役割も担います。さらに、部品を効率的に配置することで、電子機器全体の小型化や軽量化に貢献します。特定の加工を施すことで、高周波回路として機能させたり、アンテナとして利用したりすることも可能です。このように、プリント基板は単に部品を繋ぐだけでなく、電子機器の性能や構造を決定づける多様な機能を持っています。
プリント基板の構造
プリント基板は複数の層で構成されています。基本的な構造は、絶縁性の基材の上に銅箔でできた配線パターンが形成され、その表面がソルダーレジストと呼ばれる絶縁膜で覆われています。電子部品を基板に固定し、電気的に接続するための穴をスルーホールやランドと呼びます。多層基板の場合は、これらの層が複数積み重ねられ、層間の配線はスルーホールなどを介して行われます。導体層は主に銅箔が用いられ、回路パターンが形成されます。絶縁層は導体層同士のショートを防ぎ、プリプレグなどの樹脂材料で構成されます。各層が組み合わさることで、複雑な回路が実現されます。
プリント基板の主な材質
プリント基板に使用される基材は、その用途や要求される特性によって様々な種類があります。最も一般的に使用されているのは、ガラス繊維にエポキシ樹脂を含浸させたガラスエポキシ基板(FR-4)です。これは、耐熱性、強度、絶縁性に優れているため、多くの電子機器で採用されています。安価な基板としては、紙にフェノール樹脂を含浸させた紙フェノール基板があります。これは主に片面基板に用いられます。その他にも、セラミック基板や金属基板、薄く曲げることができるフィルム状の基材を使用したフレキシブル基板など、様々な材質が使われています。材質の選択は、基板の性能やコストに大きく影響するため、製品の要件に応じて適切な材料が選ばれます。



プリント基板|BuhinDana ユニバーサル基板|BuhinDana ![]()
BuhinDana では サンハヤトのユニバーサル基板、オリジナル基板製作用品をお取り扱い中です。
特注基板もご相談ください。
プリント基板の種類
プリント基板は、その構造や特性によっていくつかの種類に分類されます。主な分類としては、リジッド基板、フレキシブル基板、そしてリジッドフレキシブル基板があります。これらの種類は、それぞれ異なる特徴を持ち、様々な電子機器の設計に活用されています。
リジッド基板
リジッド基板は、硬い絶縁体基材で作られた、曲がらないタイプのプリント基板です。一般的に「プリント基板」と呼ばれる場合、このリジッド基板を指すことが多いです。リジッド基板は、部品実装が容易で、多くの電子機器で広く使用されています。
フレキシブル基板
フレキシブル基板、またはFPC(FlexiblePrintedCircuits)とは、薄いプラスチックフィルムなどの柔軟性のある材料で作られたプリント基板です。この基板は曲げたり折りたたんだりすることが可能で、可動部や限られたスペースでの配線に適しています。薄くて軽量であることも特徴の一つです。
フレキシブル基板の特徴
フレキシブル基板の最大の特徴は、その柔軟性と薄さ、軽さです。薄いフィルム状の基材を使用しているため、自由に折り曲げることができ、電子機器の小型化や軽量化に大きく貢献します。曲げても電気的特性が変化しにくく、高い信頼性を維持できるというメリットがあります。また、耐熱性にも優れた材料が使用されることがあります。設計の自由度が高まるため、複雑な形状の製品にも対応可能です。
フレキシブル基板の用途
フレキシブル基板は、その柔軟性と小型軽量性から多岐にわたる分野で利用されています。特に、スマートフォンやデジタルカメラ、ノートパソコンなどの携帯情報端末に多く採用されており、機器内部の限られたスペースでの配線や可動部に使用されています。また、車載機器や産業用ロボットなど、高い信頼性や特定の形状への対応が求められる分野でもその用途が広がっています。医療機器や航空宇宙分野など、軽量化が重要視される分野でも活用されています。
リジッドフレキシブル基板
リジッドフレキシブル基板は、硬いリジッド基板と柔軟なフレキシブル基板を一体化した構造を持つプリント基板の種類です。この組み合わせにより、部品実装に適した硬い部分と、立体的な配置や可動部に対応できる柔軟な部分を併せ持ちます。これにより、基板間のコネクタを削減できるといったメリットも生まれます。複雑な形状への対応や、限られたスペースでの高密度な配線が可能となります。モバイルデバイスや医療機器、自動車、航空宇宙など、高度な信頼性と設計自由度が求められる分野で活用されています。
層数による分類
プリント基板は、銅箔でできた配線パターンが形成されている層の数によっても分類されます。主な種類として、片面基板、両面基板、多層基板があります。層数が増えるにつれて、より複雑で高密度な回路を構成することが可能になります。
片面基板
片面基板は、基板の片面にのみ銅箔の層が形成されている最もシンプルな構造のプリント基板です。製造コストが比較的安価であるため、シンプルな回路を持つ家電製品やリモコンなど、コストが重視される製品に多く使用されています。配線は片面に限られるため、複雑な回路には向きませんが、製造が容易で信頼性が高いという利点があります。
両面基板
両面基板は、基板の表裏両方に銅箔の層が形成されているプリント基板です。表裏の配線層間は、スルーホールと呼ばれる穴の内壁にめっきを施すことで電気的に接続されています。片面基板よりも高密度な配線が可能となり、より複雑な回路を実現できます。家電製品や産業機器など、片面基板では対応が難しい比較的複雑な電子回路に広く利用されています。
多層基板
多層基板は、3層以上の銅箔の層を持つプリント基板です。基板の表裏だけでなく、内部にも配線層(内層)があり、それぞれの層間はスルーホールによって接続されます。これにより、非常に高密度で複雑な回路を小さな面積に実装することが可能になります。スマートフォンやパソコンなど、小型で高機能な電子機器に不可欠な基板です。層数が多くなるほど製造コストや設計の複雑さは増しますが、より高性能な電子機器の開発には多層基板が不可欠となっています。



プリント基板|BuhinDana ユニバーサル基板|BuhinDana ![]()
BuhinDana では サンハヤトのユニバーサル基板、オリジナル基板製作用品をお取り扱い中です。
特注基板もご相談ください。
プリント基板の設計
プリント基板の設計は、電子機器の機能を実現するための非常に重要な工程です。設計には、回路図の作成や部品の配置、配線パターンの決定などが含まれます。近年では、設計効率と精度向上のためにCAD/CAMシステムが広く利用されています。
回路設計(アートワーク)
回路設計、特にアートワークは、回路図に基づいて電子部品の配置を決め、部品間を接続するための配線パターンを基板上に描き起こす作業です。この工程では、信号の品質、ノイズ対策、放熱などを考慮しながら、最適な配線レイアウトを検討する必要があります。配線の密度や層構成もこの段階で決定され、基板の性能に直結します。
CAD/CAMの利用
プリント基板の設計および製造工程において、CAD(ComputerAidedDesign)やCAM(ComputerAidedManufacturing)システムは不可欠なツールとなっています。CADシステムを用いて回路図作成やアートワーク設計を行い、設計データをCAMシステムで製造に必要なデータに変換します。これにより、設計ミスの削減、設計期間の短縮、製造工程との連携強化が図られ、効率的かつ高品質な基板製造が可能となります。



プリント基板|BuhinDana ユニバーサル基板|BuhinDana ![]()
BuhinDana では サンハヤトのユニバーサル基板、オリジナル基板製作用品をお取り扱い中です。
特注基板もご相談ください。
プリント基板の製造工程
プリント基板の製造工程は、複数の複雑なプロセスを経て行われます。回路パターンの形成から始まり、穴あけ、めっき、表面保護といった工程を経て、電子部品が実装できる状態の基板が完成します。ここでは、一般的な製造フローと主要な工程について解説します。
製造フロー
プリント基板の製造フローは、使用する基板の種類や構造によって多少異なりますが、基本的な流れは共通しています。まず、回路パターンを形成するための準備として、基材となる銅張積層板を所定のサイズに切断します。次に、回路パターンを基板上に形成し、不要な銅箔を除去します。その後、部品を実装するための穴あけ加工や、層間を接続するためのめっき処理が行われます。最後に、表面保護や部品識別のための印刷などが施されて完成となります。
回路パターンの形成
回路パターンの形成は、プリント基板製造の最も基本的な工程の一つであり、電気信号の通り道となる配線を基板上に作り込みます。この工程にはいくつかの方法があり、主にサブトラクティブ法とアディティブ法に大別されます。これらの方法によって、設計された回路図通りの正確な配線が実現されます。また、高密度な配線が求められる場合には、めっき技術を応用した方法も用いられます。
サブトラクティブ法
サブトラクティブ法は、プリント基板の回路パターン形成において最も一般的に用いられる製造工程です。この方法では、まず基板全面に銅箔を貼り付け、回路パターンとなる部分を保護するレジストと呼ばれる膜を形成します。その後、保護されていない不要な銅箔部分を化学薬品(エッチング液)によって溶解・除去することで、回路パターンを形成します。最後にレジストを剥離して回路パターンが完成します。比較的安価で量産性に優れているため、多くのプリント基板製造で採用されています。
アディティブ法
アディティブ法は、プリント基板の回路パターン形成における製造工程の一つで、銅などの導体材料を必要な部分にのみ選択的に析出させる方法です。サブトラクティブ法とは異なり、不要な銅箔を除去するエッチング工程がないため、エッチング液の使用量を削減でき、環境負荷が少ないという特徴があります。主にめっき技術を応用して回路パターンを形成します。サブトラクティブ法に比べて微細なパターン形成に適しているとされています。
MSAP法
MSAP(ModifiedSemi-AdditiveProcess)法は、サブトラクティブ法とアディティブ法を組み合わせたプリント基板の製造工程です。まず、薄い銅箔層の上にシード層と呼ばれるごく薄い銅の層を形成します。次に、回路パターンに対応する部分にめっきを施して銅を厚くし、その後、最初に形成した薄い銅箔層とシード層の不要な部分を軽いエッチングで除去します。この方法により、より微細な回路パターンを高精度に形成することが可能となり、高密度な配線が求められる最新の電子機器に多く用いられています。
穴あけ加工
プリント基板製造において、電子部品のリード線を挿入したり、基板の層間を電気的に接続したりするために穴あけ加工が行われます。これらの穴はスルーホールやビアと呼ばれます。穴あけには、主にドリル加工が用いられますが、より微細な穴や特定の層のみに開ける穴(ブラインドビアや埋め込みビア)の場合には、レーザー加工が使用されることもあります。穴あけの精度は、部品の実装や層間接続の信頼性に直接影響するため、非常に重要な工程です。
めっき処理
プリント基板の製造工程では、穴の内壁や回路パターン表面にめっき処理が施されます。これにより、層間の電気的な接続(スルーホールの形成)を確保したり、回路パターンの導電性を向上させたりします。また、部品がはんだ付けされるランドと呼ばれる部分には、はんだ付け性を向上させたり、銅箔の酸化を防いだりするために、金や錫などの表面処理めっきが施されます。めっきの種類や厚さは、基板の用途や要求される信頼性によって異なります。
ソルダーレジストの塗布
ソルダーレジストは、プリント基板の表面を覆う保護膜であり、一般的に緑色をしていることから「緑色のインク」と呼ばれることもあります。ソルダーレジストの主な役割は、はんだ付け時に不要な部分にはんだが付着するのを防ぎ、はんだブリッジによるショートを防止することです。また、湿気やゴミ、化学物質から回路パターンを保護し、腐食を防ぐ役割も果たします。ソルダーレジストは、スクリーン印刷やスプレーなどの方法で基板に塗布され、硬化されます。
シルク印刷
シルク印刷は、プリント基板の表面に部品の識別記号や回路図の番号、注意事項などの文字やマークを印刷する工程です。部品を正確に実装したり、基板の機能を確認したりする際に役立ちます。一般的には白色のインクが使用されますが、基板の色に合わせて他の色が使われることもあります。シルク印刷によって、基板の情報が視覚的に分かりやすくなり、製造やその後のメンテナンス作業の効率が向上します。



プリント基板|BuhinDana ユニバーサル基板|BuhinDana ![]()
BuhinDana では サンハヤトのユニバーサル基板、オリジナル基板製作用品をお取り扱い中です。
特注基板もご相談ください。
プリント基板の実装
プリント基板の実装とは、製造されたプリント基板に抵抗やICなどの電子部品をはんだ付けして固定し、電気的に接続する工程です。これにより、プリント基板は電子回路として機能するようになります。部品実装にはいくつかの方法があり、それぞれ異なる技術が用いられます。
部品実装の方法
プリント基板への部品実装には、主に「表面実装」と「スルーホール実装」の二つの方法があります。表面実装(SMT:SurfaceMountTechnology)は、基板表面に部品を直接はんだ付けする方法で、部品を小型化でき、高密度な実装に適しています。スルーホール実装(THT:Through-HoleTechnology)は、基板にあけられた穴(スルーホール)に部品のリード線を差し込み、裏面からはんだ付けする方法です。部品の種類や基板の用途によって、これらの方法が使い分けられます。
はんだ付け技術
プリント基板への部品実装において、はんだ付けは電子部品と基板上の配線を電気的かつ物理的に接続する重要な技術です。一般的なはんだ付け方法には、リフローはんだ付けとフローはんだ付けがあります。リフローはんだ付けは、基板にクリームはんだを塗布し、部品を搭載した後、加熱してはんだを溶かして接合する方法で、表面実装部品に多く用いられます。フローはんだ付けは、基板の片面に部品を差し込み、溶かしたはんだ槽に基板を通して一括ではんだ付けする方法で、リード付き部品(スルーホール部品)に用いられます。また、はんだ付けを助けるためにフラックスと呼ばれる材料が使用されます。



プリント基板|BuhinDana ユニバーサル基板|BuhinDana ![]()
BuhinDana では サンハヤトのユニバーサル基板、オリジナル基板製作用品をお取り扱い中です。
特注基板もご相談ください。
プリント基板の検査
製造されたプリント基板は、設計通りに機能するか、不良がないかを確認するために様々な検査が行われます。これにより、製品の品質と信頼性を保証します。検査は製造工程の各段階や、部品実装後に行われます。
検査の種類
プリント基板の検査には、様々な種類があります。回路パターンの断線やショートを確認する導通検査やショート検査、部品が正しく取り付けられているかを確認する外観検査、電気的な特性を測定するファンクションテストなどがあります。これらの検査は、自動光学検査装置(AOI)や自動X線検査装置(AXI)、治具を用いた電気検査など、様々な装置や方法で行われます。検査を適切に行うことで、不良品の流出を防ぎ、製品の品質を確保しています。
主な不良パターン
プリント基板に発生する可能性のある不良にはいくつかのパターンがあります。製造工程で発生しやすいものとしては、回路パターンの断線やショート、めっき不良、穴あけ位置のずれなどがあります。また、部品実装時には、はんだ付け不良(はんだブリッジ、フィレット不良、はんだ不足など)、部品の誤実装や破損などが発生することがあります。さらに、基板自体の反りや変形も不良として挙げられます。これらの不良パターンを早期に発見し、原因を特定して対策を講じることが品質向上には不可欠です。



プリント基板|BuhinDana ユニバーサル基板|BuhinDana ![]()
BuhinDana では サンハヤトのユニバーサル基板、オリジナル基板製作用品をお取り扱い中です。
特注基板もご相談ください。
プリント基板の関連知識
プリント基板を取り巻く様々な知識は、基板の理解を深める上で重要です。耐久性や環境への配慮、そして類似する用語との違いを知ることで、プリント基板の全体像が見えてきます。
耐久性と寿命
プリント基板の耐久性と寿命は、使用される環境や材料、設計、そして製造品質によって大きく左右されます。高温多湿や振動などの厳しい環境で使用される基板は、特に高い耐久性が求められます。耐久性を向上させるためには、耐熱性や耐湿性に優れたガラスエポキシ樹脂などの材料を選択したり、応力が集中しないような設計を行ったりすることが重要です。多層基板は一般的に単層基板よりも耐久性が高い傾向があります。適切な材料選定と製造工程管理により、基板の寿命を延ばし、製品の長期的な信頼性を確保することが可能です。
リサイクルについて
使用済みとなったプリント基板には、銅や金などの貴金属を含む様々な材料が含まれています。これらの資源を有効活用するため、プリント基板のリサイクルが進められています。リサイクルのプロセスでは、基板を破砕し、含まれる金属や樹脂を分離・回収します。しかし、プリント基板には鉛など有害物質が含まれている場合もあり、適切な処理が必要です。環境保護の観点からも、プリント基板のリサイクル技術の開発と普及は重要視されています。
プリント配線板とプリント回路板の違い
JIS規格において、プリント基板は「プリント配線板」と「プリント回路板」の総称とされています。プリント配線板(PWB:PrintedWiringBoard)とは、絶縁基板上に導体による配線パターンのみが形成されており、まだ電子部品が取り付けられていない状態のものを指します。一方、プリント回路板(PCB:PrintedCircuitBoard)とは、そのプリント配線板に電子部品がはんだ付けなどによって取り付けられ、電子回路として機能するようになった状態のものを指します。一般的には、部品が実装された状態のものも含めて「プリント基板」と呼ばれることが多いです。
プリント基板と半導体の違い
プリント基板と半導体は、どちらも電子機器に不可欠な要素ですが、その役割と構造は異なります。プリント基板は、電子部品を物理的に固定し、部品間を配線で接続するための「基盤」の役割を果たします。一方、半導体(ICチップなど)は、トランジスタなどの微細な電子素子を集積したものであり、計算や情報処理などの特定の「回路」機能を持つ「部品」そのものです。半導体はプリント基板の上に搭載され、プリント基板の配線を通じて他の部品と接続されることで、電子機器全体の複雑な回路が構成されます。



プリント基板|BuhinDana ユニバーサル基板|BuhinDana ![]()
BuhinDana では サンハヤトのユニバーサル基板、オリジナル基板製作用品をお取り扱い中です。
特注基板もご相談ください。
プリント基板業界
プリント基板はあらゆる電子機器に不可欠な部品であるため、プリント基板業界はエレクトロニクス産業において重要な位置を占めています。市場動向や主要なメーカーを知ることは、業界の理解に繋がります。
市場動向
プリント基板市場は、スマートフォン、パソコン、自動車、産業機器など、様々な電子機器の需要に影響を受け変動しています。近年では、5Gの普及に伴う通信機器向け基板の需要増加や、自動車の電装化・CASE(Connected,Autonomous,Shared,Electric)化の進展による車載用基板市場の拡大が顕著です。また、IoTデバイスやウェアラブル端末の普及も市場を牽引しています。技術的には、より高密度で高速な信号伝送に対応できる多層基板や高機能基板の需要が高まっています。
主なメーカー
プリント基板のメーカーは世界中に存在し、様々な種類の基板を製造しています。日本国内にも多くの有力なプリント基板メーカーがあり、高い技術力を持っています。これらのメーカーは、民生品から産業機器、車載、宇宙開発など、幅広い分野向けに多様なプリント基板を提供しています。また、特定の種類の基板や、短納期対応などを強みとするメーカーも存在します。




プリント基板|BuhinDana ユニバーサル基板|BuhinDana ![]()
BuhinDana では サンハヤトのユニバーサル基板、オリジナル基板製作用品をお取り扱い中です。
特注基板もご相談ください。